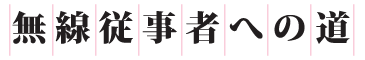第5章 試験当日の心構えと注意事項
試験日が近づいてきますと、目に見えない緊張感がからだ全体に張りつめてくるのは、やむを得ないことです。普段以上に健康に気をつけることが大事ですが、特に試験前日は勉強を切り上げて、ゆったりとした心構えで熟睡することをおすすめします。ジタバタしても始まらないという気持ちが、好結果を生む場合が多いものです。
- 試験場には、時間に十分ゆとりをもって到着するようにしましょう。交通事情を考え、早目に家を出て、試験場に慣れ、落ち着いた気分で受験したいものです。なお、試験場には駐車場はありませんので、車での来場はできません。
- 受験票を忘れていないか確認しましょう。忘れると受験できないことがありますから、受験期間中は朝の出発前に確認を怠らないように。
- 筆記用具として、鉛筆(シャープペンシルも可)、消しゴムは必ず持参しなければなりません。なお、試験場での電卓及び計算尺の使用は禁止されていますので注意してください。
- 電気通信術(電信の送信)の試験では、協会が用意した電鍵を使用することとなっていますが、自己の使い慣れたものを使用する方が心配ないでしょう。その場合、事前に試験員に申し出て許可を得ることを忘れないでください。
(公財)日本無線協会では、受験される方への注意として次のように呼びかけています。
① 受験者は、必ず印刷した受験票を携行し、試験開始時刻15分前までに試験室に入るようにしてください。なお、英会話のある英語の試験や電気通信術の試験については、試験開始時刻以降の入室はできませんので、遅れないようにしてください。
② 答案用紙(多肢選択式による筆記試験の場合に限る)には、HBまたはBの鉛筆を使って氏名を漢字で、受験番号・生年月日を算用数字で記入し、受験番号・生年月日・解答をマークする(塗りつぶす)ことになっています。なお、消しゴムはプラスチック製のものに限って使用できます。
③ 答案用紙は、白紙の場合でも必ず提出してください。
5-2 答案用紙の書き方
●多肢選択式問題の場合
電気通信術以外の試験科目においては、試験問題は多肢選択式となっており、答案用紙はマークシート方式を採用しています。試験問題の複数の選択肢の中から正しいと思うものを一つ選ぶ解答方式です。二つ以上を選択すると、その中に正答が含まれていたとしても採点されませんので、気を付けてください。
マークシートにマークする場合は、該当のマーク欄をきれいに塗りつぶしてください。マークし直す場合は、前に塗りつぶしたマークをきれいに消しておかないと二つマークしたものと間違われ不正解となるおそれがありますので、十分気をつけてください。
●電気通信術の場合の場合
電気通信術の試験においては、受信・受話は、CDに録音された試験問題を再生して受験者に聞かせ、その内容を答案用紙(受信・受話用紙)に書き取らせる方法で行います。このため、受信では、和文及び欧文(暗語及び普通語)の試験問題について、また受話の場合は欧文(暗語)の試験問題について、それぞれに適した答案用紙が使用されます。
答案への記入に当たっては、試験前に試験執行員から具体的に注意事項の周知が行われますので、それに従って記入することが大切です。なかでも注意したいのは、受信・受話した文字は誰がみても判別できるよう記入すること、例えば、和文でいえばニと二(数字)、ハと八(数字)、シとツ、ソとンなど、欧文では筆記体のaとd、bとf、eとc、gとqなど字体が似ているものの記入には注意した方がいいでしょう。
5-3 電気通信術
●電気通信術
電気通信術の試験については、無線従事者規則第3条に基づき試験の方法が告示されており、試験を実施している協会においてもこの告示に基づいて試験を行っています。試験は、モールス電信による送・受信、電話の送・受話及び直接印刷電信による送信の三つの試験項目があり、受験する資格によって課される試験項目が異なっています。
なお、モールス電信による送・受信は、無線局運用規則の別表第一号に定める和文及び欧文のモールス符号を使用し、電話の送・受話は、同別表第五号に定める欧文通話表によって試験が行われます。
1 試験方法と試験対象資格
① モールス電信による送・受信
モールス符号を使用し、電鍵(キー)操作により電文の送信を行い、また音響にしたモールス符号を文字として受信用紙に書き留める方法で受信を行うこととなっています。受信の試験は同じ試験室の受験者に対して一斉に行われます。送信の試験は試験員と個々の受験者が対面して行われます。一・二・三総通及び国内電の資格が対象です。
② 電話
欧文通話表を使用して電話の送・受話を行うこととなっています。受話の試験は受験者に対して一斉に行われ、送話の試験は試験員と個々の受験者が対面して行われます。一・二総通、一・二・三海通、航空通、一海特及び航空特の資格が対象です。
③ 直接印刷電信
試験問題として示される電文(欧文)を試験機器(パソコン)のキーボード操作により入力(送信)する方法で行うこととなっています。試験は個々の受験者の試験卓に試験員が同席する形で行われます。一総通及び一・二・三海通が対象です。
2 試験の実施順序
試験の実施順序については、実際に試験を行っている協会本部での実施例をみてみたいと思います。
① 一・二・三総通の場合
モールス電信の受信、電話の受話(三総通を除く。)の試験を行った後、一総通のみ直接印刷電信の送信の試験が行われます。その後、モールス電信の送信及び電話の送話(三総通を除く。)の試験が行われます。
② 一・二・三海通の場合
電話の受話の試験を行った後、直接印刷電信の送信の試験が行われます。その後、電話の送話の試験が行われます。
③ 航空通、一海特及び航空特の場合
航空通の場合は、電話の受話の試験に引き続き送話の試験が行われますが、一海特や航空特においては受話試験の後に工学、法規等の学科試験が行われ、その後に電話の送話の試験が実施されます。
④ 国内電の場合
上述③と同様、モールス電信の受信の試験の後、法規の学科試験が行われ、その後にモールス電信の送信の試験が行われます。
3 試験に際しての注意事項等
(1) 受信・受話試験- 配布された受信・受話用紙には、練習用紙を除いて、用紙下部における資格、受験番号及び氏名の各欄へ記入を行ってください。受信用紙は複数枚配布されますので、全ての用紙に記入してください。記入には鉛筆、ボールペン、万年筆などの使用ができますが、赤色のものは使用できません。
- 試験前に使用するCD再生機を使って音量調整などの受信・受話状況の確認が行われます。聞きづらい、音が小さい等気になることがあれば試験員へ申し出て改善等を求めることができます。
- 試験方法、答案の書き方などについて、予め試験員から説明がありますが、不明な点についてはその都度試験員に尋ねましょう。試験開始後は一切の質問等は受け付けてもらえませんので、試験前に不明点など解消しておきましょう。
- スマホ、携帯電話等の音を発するものの電源は必ずOFF(断)にし、カバンなど荷物の中に収納しておきましょう。試験中は、アラーム音やバイブの振動音のような小さな音であっても試験への集中力を削ぐだけでなく、周りの受験者への大きな迷惑となります。
- 受信の試験では、先ず練習文が再生され、引き続き試験問題が再生されてきます。それぞれ「レンシュウ」や「シケン」の符号の後、和文や欧文など電文の種類についても前置されますので、使用する受信用紙を間違えないよう注意しましょう。なお、電話の受話の場合は、練習用紙の配布はありませんので、練習文はただ聞き流すだけにしてください。
- 試験中は、他の受験者の迷惑となるような行動、発声などは絶対にしないでください。
- 受信の電文は複数通あります。受信用紙の記載面に書ききれない場合は、裏面などに記載することもできます。
- 試験終了後、一定時間をおいた後、試験員から筆記具を置くよう指示がありますので、直ちにその指示に従ってください。受信用紙は白紙のものを含めすべて提出してください。
- 送信・送話試験についても、試験開始後は試験員への質問は一切受け付けてもらえませんので、試験方法等不明なことは事前に試験員に尋ねておきましょう。
- モールス送信の試験では、協会が用意した電鍵を使用することになっていますが、自分で持ち込んだ電鍵の使用も認められています。その場合、予め試験員に申し出て、使用する電鍵の機能(例:一の動作で自動的に符号を生成、送出する機能があるか)、オシレータへの接続の可否などの点検、確認を受ける必要があります。試験当日に慌てないよう、事前に協会へ照会し、使用の可否について確認をとっておいた方がいいでしょう。
- 試験は協会が用意する試験用機器の故障などがない限り中断できません。自己都合による中断は認められないので、持ち込んで使用する電鍵については常に最適な動作をするよう日頃から調整しておいた方がいいでしょう。
- 直接印刷電信の送信の試験は、協会が用意した試験用機器(パソコン)を使用し、キーボード操作により試験問題(電文)を打込み(送信)していく方法で行われますので、試験で使用する文字や数字等のキー以外の他のキー操作はしないよう注意してください。試験前に練習したい場合は、試験員に申し出れば可能です。